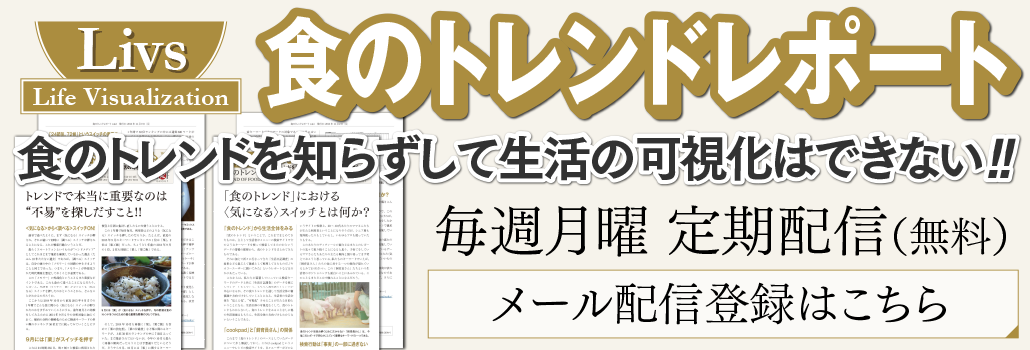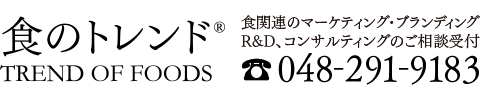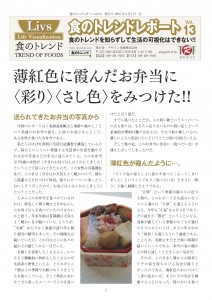【目次】〈食べたい力〉を〈食卓力〉につなげたヤオコーの弁当!
- ヤオコーのお弁当
- 「メインディッシュ」病?!
- 「漬物」という〈季節感〉
- 〈食卓力〉に注目
食のトレンドレポートVol.14が配信されました。総菜売場に並ぶ多彩なお弁当の数々。皆さまの中には、主菜がお弁当の価値を決めると考える方はいらっしゃるでしょうか。もしかすると、それは「メインディッシュ」病かもしれません。今やお弁当は携帯食糧としてだけではなく、中食の一部として家庭の食卓に並ぶものになりました。本当のお弁当の価値は、お弁当が食卓でどんなシーンを形成し、どんな欲求を満たしているかを捉えることで見えてきます。「焼魚弁当」とも「筑前煮」の惣菜パックとも違う本来の「お弁当」の価値を、ヤオコー(スーパーマーケット)のお弁当が出現したある方の生活シーンから、特徴的なエッセンスと合わせて抽出します。お弁当が出現する食卓で、シニアがどのように「季節」や「旬」を演出しているかも合わせて解説します。本号の最後には、ある78歳のシニア女性の一日の生活の詳細がわかる日記調査結果を付録しました。生活の中で食卓がどのように形成されていくか、どのようなきっかけでお弁当が選択されるのか、生活の断片から読み取っていただける内容になっています。まだご登録がお済みでない方も、ぜひご登録してお読みください。豊かな食提案の一助になることを願っています。
本編はご登録者限定「食のトレンドレポート」で送らせていただきます。PDF添付にてメール配信いたします(無料)。定期配信登録はこちらからお願いいたします。
定期配信登録をいただいた方は過去のレポートもすべて無料でお読みいただけます。登録者専用の過去レポートダウンロードページを次回配信時にお伝えいたします。是非過去レポートも合わせてお読みください!