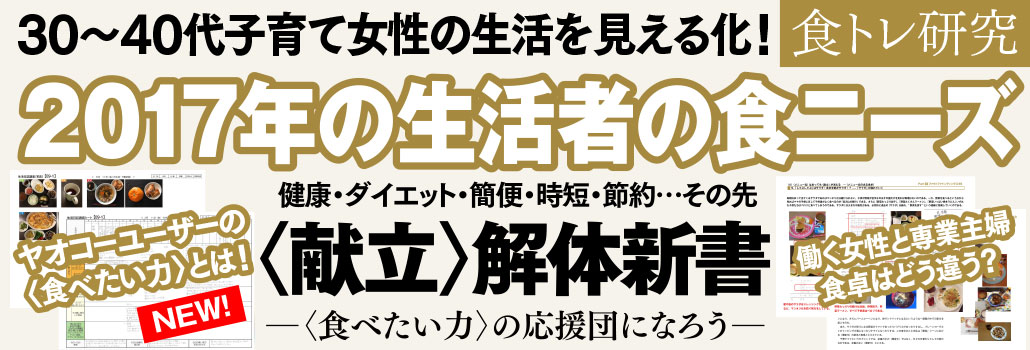環境に優しい地場野菜コーナー
 農産物直売所ビジネスの売上高が1兆円に迫っていることは前回お伝えした通りだ。復習を兼ねておさらいすれば、農産物の直売が増えた一つの要因は、産地での直売所(ファーマーズマーケット、道の駅など含む)の増加にある。真剣に事業展開しているファーマーズマーケットや道の駅では、旅行代理店に営業をかけ観光バスの呼び込みを積極的に行っている。その結果、年齢を問わず女性の多い観光バスが道の駅に着くと、彼女たちは先を争って農産物直売所に殺到、鮮度が良くて割安な野菜を買い込むことになる。帰りの足は確保されているから、少しぐらい多めに買っても平気だ。ご近所におみやげ代りに配れば野菜は喜ばれる。
農産物直売所ビジネスの売上高が1兆円に迫っていることは前回お伝えした通りだ。復習を兼ねておさらいすれば、農産物の直売が増えた一つの要因は、産地での直売所(ファーマーズマーケット、道の駅など含む)の増加にある。真剣に事業展開しているファーマーズマーケットや道の駅では、旅行代理店に営業をかけ観光バスの呼び込みを積極的に行っている。その結果、年齢を問わず女性の多い観光バスが道の駅に着くと、彼女たちは先を争って農産物直売所に殺到、鮮度が良くて割安な野菜を買い込むことになる。帰りの足は確保されているから、少しぐらい多めに買っても平気だ。ご近所におみやげ代りに配れば野菜は喜ばれる。
もう一つの要因は、いまやスーパーマーケットでも直売の野菜が手軽に買えるようになったことだ。1980年代後半から、大手スーパーを中心にその店頭には産地直送野菜が並んでいた。しかし、これらの商品は有名産地の野菜であり、地場野菜ではなかった。その流れが大きく変わったのは、環境問題が関心事となり、地産地消が話題になり始めてから。つまり産地直送であっても遠くから運んでいたのでは輸送に負荷もかかり環境に優しくない。それよりも地元で栽培した野菜やフルーツを地元で消費したほうが、よりナチュラルで持続性の高い仕組みだということになったのだ。
スタンダードになったスーパーの野菜直売コーナー
こうしてスーパーマーケットの青果売場は、バイヤーが青果市場で仕入れた商品、有名産地と契約栽培した野菜、地元の農家が持ち込んだ商品が品揃えされるのが当たり前となった。そのなかで地場野菜は顔の見える野菜として人気があるため、そのことがうまく伝わるように、POPをつけてコーナー展開されるのが一般的になっている。
ちなみにスーパーマーケットが、地場野菜の直売所を設置するには、おおざっぱにいえば三つほどの方法がある。最も手間がかからないのは、地元の農協(JA)にコーディネートを頼んでしまうことだ。するとJAが必要な数の農家に話を通し、毎日必要な量の野菜を生産者が直接納品してくれるようになる。また最近は、農業総合研究所(和歌山市)のように、農家から集めた野菜や果物をIT技術を使って全国のスーパーに効率よく届ける企業が、東京証券取引所のマザーズ市場に上場するほどに力をつけてきており、同研究所の野菜をうまく組み合わせれば、自分たちで農家と接点を持たなくても、地場野菜の直売所をコーナー展開できる。
 二つめの方法はSMチェーンと農家が個別に契約し、農産物直売所コーナーをつくるやり方だ。例えば茨城県を中心に関東に約160店舗を出店しているカスミでは、そのうち約60店舗で直売所をコーナー展開している。カスミの農産物直売所で自分が栽培した野菜を販売したいと考えた生産者は、まずカスミのサイトに申し込みをし、生産している作物やその量、栽培時期、納品したい店舗など、いくつかの項目をすり合わせたうえで、契約が成立すれば納品、販売が始まる。栽培から収穫、パッケージ化して値付けした商品の納品までを生産者が行い、売価の82~83%が生産者の取り分、残りが手数料や場所代としてカスミのものになる。この比率はJAの直売所や道の駅とほぼ同じだ。
二つめの方法はSMチェーンと農家が個別に契約し、農産物直売所コーナーをつくるやり方だ。例えば茨城県を中心に関東に約160店舗を出店しているカスミでは、そのうち約60店舗で直売所をコーナー展開している。カスミの農産物直売所で自分が栽培した野菜を販売したいと考えた生産者は、まずカスミのサイトに申し込みをし、生産している作物やその量、栽培時期、納品したい店舗など、いくつかの項目をすり合わせたうえで、契約が成立すれば納品、販売が始まる。栽培から収穫、パッケージ化して値付けした商品の納品までを生産者が行い、売価の82~83%が生産者の取り分、残りが手数料や場所代としてカスミのものになる。この比率はJAの直売所や道の駅とほぼ同じだ。
最後のパターンが、SMチェーンと生産者グループが手を組んで農産物直売所を運営するパターンだ。例えば静岡の静鉄グループのSMチェーンであるしずてつストアでは、地元の生産者グループ「静農会」とがっぷり四つに組んで地場野菜・果実の販売に取り組んでいる。静農会は静岡県の東部地区から西部地区までの16グループで構成されており、生産者は約240人いる。しずてつストアの各店舗には「静農会」の青果物が必ずコーナー展開されており、「この季節であれば、静農会コーナーにはあの商品が並ぶ」ことがわかっているので楽しみいしている顧客も多い。特定の生産者グループと組むメリットは、レベルの高い野菜・果物を確保できること。生産者グループに入っている農家は、優れた栽培技術や安全・安心に対する意識を共有した篤農家が多い。
農産物直売所を身近なものにした「わくわく広場」
しかし、スーパーマーケットで地場野菜がコーナー展開されていても、それが直売所と意識されているかどうかはやや疑問だ。確かに生産者の顔写真をPOPに入れたりして、いかにもそれらしい雰囲気になっているが、スーパーで買物する人にとっては、あくまで野菜のちょっと変わった売り方にすぎず、バスツアーで乗り付けたファーマーズマーケットとは別物と思われている恐れが十分ある。
それに対して非日常的なファーマーズマーケットや道の駅での買物を、日常性のなかに位置付直して成功しつつあるのが(株)タカヨシが展開している「わくわく広場」だ。同店は農産物の委託販売をメーンに、自社仕入れの伝統的な加工食品を合わせて販売するフォーマットの店舗。成城石井や北野エース、こだわり屋など高質の加工食品を中心にした専門店は過去にもあったが、委託販売の野菜・果物を前面に出した店舗はこれまでなかった。
 このようなフォーマットの店舗をタカヨシが開発したのは、同社の成り立ちに負うところが大きい。もともと同社は千葉のホームセンター(HC)チェーンだったが、1990年代に入って競合店が売場面積1万m²を超える大型店となり、2,000m²前後と狭いタカヨシは競争に埋没、厳しい戦いを余儀なくされた。そこで同社が苦肉の策として取り入れたのが、売場の一部を地元農家に提供して始めた野菜の委託販売。これが予想以上に当たったため、やがて農産物の委託販売を主体とする業態に変わっていった。
このようなフォーマットの店舗をタカヨシが開発したのは、同社の成り立ちに負うところが大きい。もともと同社は千葉のホームセンター(HC)チェーンだったが、1990年代に入って競合店が売場面積1万m²を超える大型店となり、2,000m²前後と狭いタカヨシは競争に埋没、厳しい戦いを余儀なくされた。そこで同社が苦肉の策として取り入れたのが、売場の一部を地元農家に提供して始めた野菜の委託販売。これが予想以上に当たったため、やがて農産物の委託販売を主体とする業態に変わっていった。
タカヨシがHC企業から、現在のような農産物委託販売ビジネスに正式に業態転換したのは7年前の2010年のこと。「わくわく広場」は、最初千葉県内の小型ショッピングセンター(SC)などへの出店が多かったが、やがて大型SCのイオンモールなどへの出店が始まった。「わくわく広場」各店舗の売上は年を追ってアップ、既存店の成長力がSCディベロッパーの間で注目され、出店要請が相次ぐことになった。「わくわく広場」は16年11月現在81店舗まで増えているが、17年2月期は年間30店舗以上の出店が予定されている。このままいけば、同社は17年2月期には100店舗を超えそうだ。
「わくわく広場」が好調なのは、野菜や果物を前面に出すことによって、農産物直売所であることが一目瞭然にわかるつくりになっていること。青果のちょっと変わった売り方に見えてしまうスーパーマーケットはその点不利だ。また生産地に近い場所にあるため、日常的に利用するのが難しいファーマーズマーケットや道の駅と違って、消費者の生活の場に近い大都市近郊のSCに出店していることが「わくわく広場」の存在感を高めている。つまり、これまで大型SCのスーパーマーケットで野菜を買っていた消費者が、鮮度の良さやおいしさに魅かれて「わくわく広場」で青果物を購入するようになり、同社の売上は急伸しているのだ。
「わくわく広場」が伸びれば、同じような発想のチェーンや少し形を変えた業態が出てくる可能性もある。そうなれば農産物流通で、直売の比率がますます高くなることが考えられる。いま主流の系統出荷もその地歩は決して盤石ではない。
執筆:山口 拓二
第12回<予定>「『中食』の誕生」