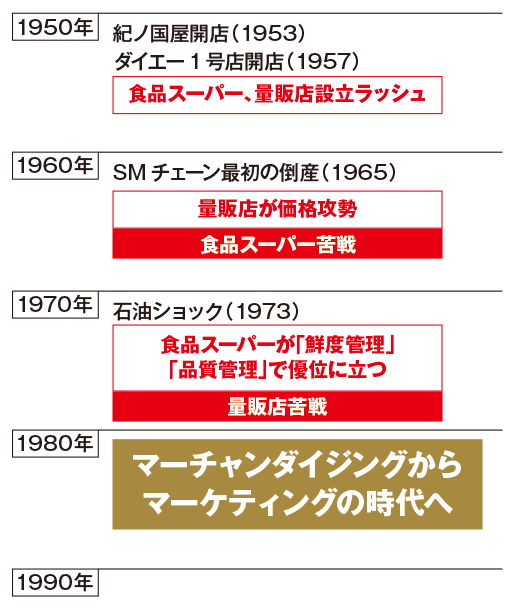2500人に1店舗まできたコンビニの店舗密度
 ミスターコンビニともいわれたセブン&アイHDの鈴木敏文氏が83歳でついに退任した。1970年代初頭、伊藤忠商事が持ち込んだコンビニの日本での展開を決断したことは、いまでこそ勇断といわれているが、当時はイトーヨーカ堂社内でさえ、ほとんど相手にされていなかった。1970代初頭といえば量販店(GMS)の成長が本格化した時期であり、イトーヨーカ堂も首都圏を中心に東日本で大量出店、売上高は一気に1兆円を超えた。
ミスターコンビニともいわれたセブン&アイHDの鈴木敏文氏が83歳でついに退任した。1970年代初頭、伊藤忠商事が持ち込んだコンビニの日本での展開を決断したことは、いまでこそ勇断といわれているが、当時はイトーヨーカ堂社内でさえ、ほとんど相手にされていなかった。1970代初頭といえば量販店(GMS)の成長が本格化した時期であり、イトーヨーカ堂も首都圏を中心に東日本で大量出店、売上高は一気に1兆円を超えた。
そのような状況下、1973年11月に(株)ヨークセブン(現セブン-イレブン・ジャパン)を設立、翌年の5月に1号店の豊洲店をオープンさせたセブン-イレブンだが、当初は現在のコンビニとは大きく違ったフォーマットだった。まして相前後して事業会社を設立しコンビニの展開に乗り出したローソン(ダイエー)、ファミリーマート(西友)は、スーパーマーケットの感覚でコンビニを経営していたため、ミニスーパーの域を出なかった。恐らく鈴木敏文氏を含めて関係者は、コンビニが店舗数で5万店、販売高で10兆円を超える規模にまで成長するとは誰も考えていなかったはずだ。
1985年前後だったと思うが、雑誌の取材でセブン-イレブンの店舗開発担当の役員に会った時、コンビニはどこまで増えるかという話になったことがある。具体的な店舗数は出なかったが「人口1万人に1店舗程度ですか」という問いに否定の言葉はなかった。当時セブン-イレブンは2,000店舗台、業態全体でも7,000店舗台だった。1万人に1店舗なら約1万3,000店舗だが、その程度のイメージしか浮かばなかったのであろう。人口2,500人に1店舗(2014年時点)までコンビニが増えるとは、当時経営の中枢にいた人でもわからなかったということだ。
大きく変わったコンビニの店舗フォーマット
セブン-イレブンの日本での1号店がオープンした1974年5月は、筆者が大学4年生の時。1976年2月期末のコンビニの店舗数は全チェーンを合わせても120店舗なので、スタート時点の出店は微々たるものだった。コンビニ創世記は、それほど注目して見ていたわけではないので明確な記憶はないのだが、品揃えは今よりもグローサリーが多かったように思う。ガソリン販売を柱に飲料や加工食品主体の商品構成だったアメリカのセブン-イレブンをモデルにした、日本のセブン-イレブンの当初のフォーマットがグローサリー寄だったことは当然といえば当然。カウンターオペレーションで、ドリップコーヒーを販売していたが、保温していると煮つまり、廃棄直前に購入した場合は、悲惨な香りだった記憶がある。
コンビニの潮目が変わったのは1970年代後半から。セブン-イレブン・ジャパンでいうと1980年11月に1,000店舗を突破、以後順調に店舗数を増やしていく。
顧客ニーズに合わせた「商品の引っ越し」
 その理由はこの時期に日本のコンビニのフォーマットが変わり、弁当、おにぎり、サンドイッチなども扱う現在のMDに近づいたから。コンビニが弁当やおにぎりなどを品揃えするまでは、これらを購入できる場所は限られていた。例えば弁当でいえば、まず思い浮かぶのは駅弁であり、あとは商店街の総菜屋や仕出し弁当など。おにぎりは商店街の和菓子屋でも扱っていたが、日本を代表するファストフードとして市民権を得たのは1978年にセブン-イレブンで扱い始めてから。
その理由はこの時期に日本のコンビニのフォーマットが変わり、弁当、おにぎり、サンドイッチなども扱う現在のMDに近づいたから。コンビニが弁当やおにぎりなどを品揃えするまでは、これらを購入できる場所は限られていた。例えば弁当でいえば、まず思い浮かぶのは駅弁であり、あとは商店街の総菜屋や仕出し弁当など。おにぎりは商店街の和菓子屋でも扱っていたが、日本を代表するファストフードとして市民権を得たのは1978年にセブン-イレブンで扱い始めてから。
しかし、最初はおにぎりは家庭で手づくりするものという既成概念があり、人気商品とはいえなかった。それが1984年に現在のようなパラシュート型包材のおにぎりが新発売されたあたりから売上に弾みがつき、2014年2月にはセブン-イレブンだけで年間18億7,600万個も売り上げる大ヒット商品となった。他のコンビニチェーンも合わせれば、年間30億個前後は売れているはずだ。単純平均すれば日本人1人当たり20個以上コンビニのおにぎりを食べていることになる。
つまりセブン-イレブンをはじめとするコンビニでは、弁当やおにぎりなどを競合業種や家庭から引っ越しさせることで売上を拡大したのだ。そしてこのような「商品の引っ越し」は、ファストフードや惣菜だけではなく、飲料やアイスクリーム、スイーツなどに及び、直近では入れたてコーヒーをカフェ(喫茶店)や缶コーヒーからシフトさせることに成功した。セブン銀行のATMでは、お金をおろしたり、振り込みしたりといったサービスニーズまで引っ越しさせた。
「中食の誕生」時期にコンビニが登場
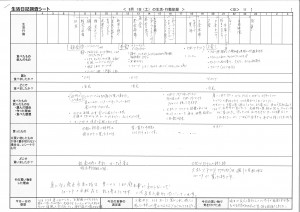
しかし、商品を引っ越しさせるほどのムーブメントとなるためには、その背景となる要因がなければならない。それで思い出すのが筆者が1983年から参加した(株)ネクストネットワークのヤング層を対象とした定性調査「生活カレンダー」の分析をしていた時感じた食生活の変化だ。ちなみにこの「生活カレンダー調査」は、15~25歳までの男女50人にモニターになってもらい、毎月1週間の生活の記録をフォーマットに合わせて1年間書いてもらうというもの。生活カレンダーを書いてもらう前には、各モニターのプロフィールを知るために、2時間程度のデプス(深層)インタビューも行っていた。
この「生活カレンダー調査」が始まったのは1983年4月のこと。食品、飲料、乳製品、住宅設備などのメーカーに会員になってもらい、毎月1回研究会を行っていた。この調査が3年目に入った頃だと思うが、カレンダー上に記述された現象面をレポートするだけではなく、食シーンを定量的に分析してみようということで、50人のモニターの1年間の食シーン約1万7,000回を「内食」「外食」「その他」に分類してみた。
その時感じたのは、きれいに「内食」「外食」に分類されない「その他」の食シーンが思いのほか多いなということ。具体的には高校の教室や大学の中庭であったり、職場近くの公園やオフィスの自分のデスクなどで、かなりの頻度食事やおやつを食べていた。その集計を前にして、日本人の食シーンは「内食」「外食」という二次元的な分類では割りきれなくなっており、内食と外食の間を「中食」としなければ全体像は見えなくなってきているのではないかといった議論をしたことを憶えている。
「中食」がコンビニ業態の成長を担保した
これが1985年頃のこと。いまや日本の食を語る上で欠かすことのできない「中食」の概念の発見としてはかなり早い時期だったのではないかと思う。ただ「中食」を誰が言い出したかなどはさして重要な問題ではない。それよりも大事なことは、1985年頃には「中食」シーンはかなり浸透しつつあり、それから推測すれば1970年代後半からは、少しずつ「中食」シーンのボリューム化が進んでいたのではないかということ。つまりセブン-イレブンが1978年に手巻きおにぎりを発売、弁当やサンドイッチの販売にも力を入れ始めた時期は、食シーンとしての「中食」の台頭と見事に一致していたのだ。見方を変えればコンビニの「商品の引っ越し」は偶然の産物ではあるが、それでもこの二つが「中食の誕生」と軌を一つにしたことで、その後のコンビニ業態の快進撃につながったことは間違いない。
要するにコンビニ業態は、ただなんとなく伸びたのではなく、おにぎりや弁当、惣菜などによって、それまで外食などに流れていた食シーンを取り込めたことで大きく成長したのだ。逆にいえばコンビニ業態の売上高が、百貨店業態やGMS業態を抜き、SM業態に迫りつつあるのは、日本人の食シーンの変化からすれば必然でもあったといえる。
【参考データ】惣菜市場規模 業態別推移と外食率・惣菜率
執筆:山口 拓二
第4回<予定>「おかず屋」「ハーフデリ」「惣菜」
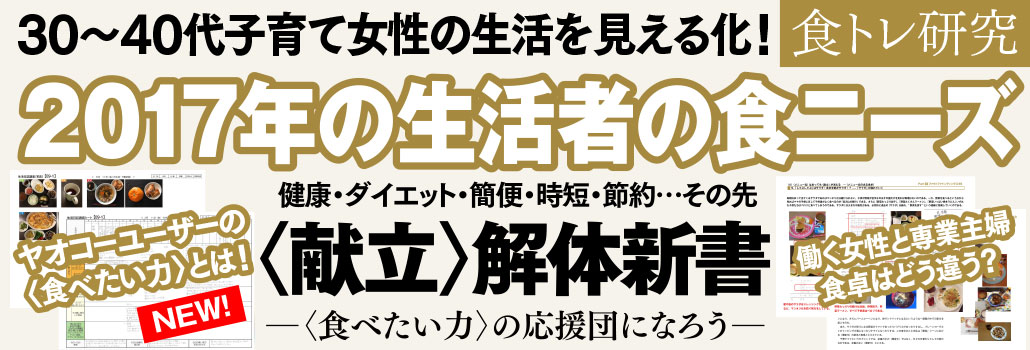





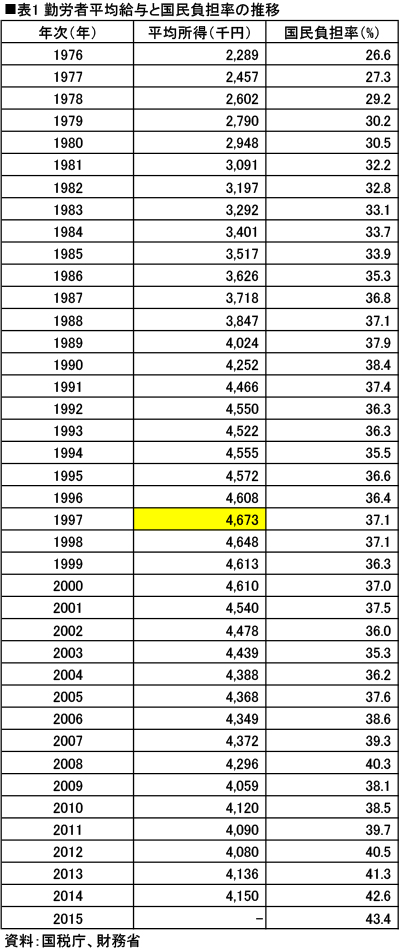
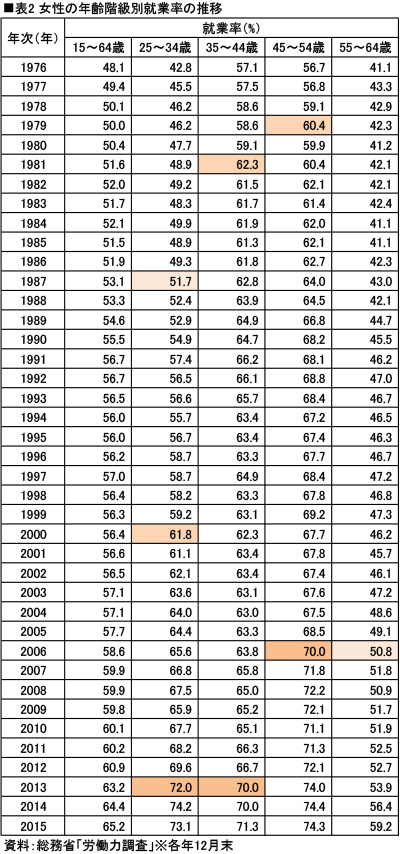
 首都圏のスーパーマーケット(以下SM)では、ヤオコーの評判がいい。一時期「ヤオコーの商品は高い」といったネガティブキャペーンで苦しんだが、最近は加工食品や飲料などについても、ディスカウントSMに負けない価格設定で競合店に付け込むスキを見せていない。野菜をはじめとする生鮮食品の価格もリーズナブルだし、2分の1カット、4分の1カット販売も当たり前になっているキャベツや白菜のプライシングも、フルサイズ価格の半分、4分の1であり、小容量になるほど高くなる店舗に比べるとフェアプライスに徹している。
首都圏のスーパーマーケット(以下SM)では、ヤオコーの評判がいい。一時期「ヤオコーの商品は高い」といったネガティブキャペーンで苦しんだが、最近は加工食品や飲料などについても、ディスカウントSMに負けない価格設定で競合店に付け込むスキを見せていない。野菜をはじめとする生鮮食品の価格もリーズナブルだし、2分の1カット、4分の1カット販売も当たり前になっているキャベツや白菜のプライシングも、フルサイズ価格の半分、4分の1であり、小容量になるほど高くなる店舗に比べるとフェアプライスに徹している。 ニッショーストアが1980年代半ば以降に、注目されるようになったことを説明するには、その前提として1960年代、1970年代の関西のスーパー業界の競合状況が、どのようなものだったかを知ってもらう必要がある。1950年代から1960年代前半にかけて、ダイエー、岡田屋(現イオン)、ニチイ(旧マイカル)、イズミヤなどGMSチェーンになっていく企業や関西スーパーマーケットなどSM企業が続々設立された。そして1960年代は大量仕入れ、大量販売を武器にダイエーをはじめとするスーパーストアが価格攻勢に出たため、食品スーパーは完膚なきまでに叩きのめされることになった。
ニッショーストアが1980年代半ば以降に、注目されるようになったことを説明するには、その前提として1960年代、1970年代の関西のスーパー業界の競合状況が、どのようなものだったかを知ってもらう必要がある。1950年代から1960年代前半にかけて、ダイエー、岡田屋(現イオン)、ニチイ(旧マイカル)、イズミヤなどGMSチェーンになっていく企業や関西スーパーマーケットなどSM企業が続々設立された。そして1960年代は大量仕入れ、大量販売を武器にダイエーをはじめとするスーパーストアが価格攻勢に出たため、食品スーパーは完膚なきまでに叩きのめされることになった。 しかし、ここまでであれば「価格」のダイエー(スーパーストア)に対して「クォリティ」の関西スーパーマーケット(SM)と、それぞれの業態が自分の得意とする所を活かして、食品販売の主導権を取ろうとした話にすぎない。それが1980年代に入って、ニッショーストアがSMの運営にマーケティングを導入してから様相が一変する。つまり、それまではGMS(スーパーストア)であれ食品スーパーであれ、マーチャンダイジングはあってもマーケティングはなかったのだ。
しかし、ここまでであれば「価格」のダイエー(スーパーストア)に対して「クォリティ」の関西スーパーマーケット(SM)と、それぞれの業態が自分の得意とする所を活かして、食品販売の主導権を取ろうとした話にすぎない。それが1980年代に入って、ニッショーストアがSMの運営にマーケティングを導入してから様相が一変する。つまり、それまではGMS(スーパーストア)であれ食品スーパーであれ、マーチャンダイジングはあってもマーケティングはなかったのだ。